空いているベンチを見つけてクレープをゆっくり食べたあと、陽光できらきら輝く青い海を眺めつつ、
そろそろ帰ろっか……荷物も重いし。
などと考えていると、かかとに何かがぶつかる感触があった。
怪訝に思ってベンチの下を覗くと、ちょうど彼女の足元にサッカーボールが一つ転がっている。
ボールを持って立ち上がり、振り返ると、ベンチの背もたれのむこうに三歳くらいの小さな男の子がこちらへとことこ早足で近づいてくるのが見えた。
彼の背後には、父親らしい男性が、同様にこちらに視線を投げ、すみません、というように苦笑して頭を下げている。
紅子はボールを持ち主の少年に手渡すべく、ベンチの向こう側へ回った。
「はい、どうぞ」
かがんでボールを手渡すと、少年と目が合った。
黒い瞳と、黒い巻き毛。
日本人離れした鼻筋と、白い肌。
その顔を見た刹那、闇の中で閃いた稲妻がほんの一瞬辺りを照らすように、ある男の顔が紅子の脳裏をよぎった。
白い顔を縁取る黒く長い巻き毛、だがその黒い瞳は、光を失った暗黒の深淵――
誰?
思い出そうとした次の瞬間、それはするりと再び記憶の闇に沈んで消えた。
ただ一つ、その左頬に浮かぶ小さな傷跡を残して。
それは少年の左頬にもあった。
「そのケガ……」
紅子が我知らずつぶやくと、
「あのねえ、おじいちゃんちのろうかで、すべってころんだの」
少年はボールを受け取りながらはにかんで答えた。
と、そのとき、まるでそれ以上彼らが会話するのを拒むように、ハスキーな女性の声が聞こえた。
「あなた、泰己(たいき)」
少年が声のほうをくるりと振り返るのに合わせて、紅子は彼の視線を追いかける。
そこには、ベビーカーを押してこちらへやってくる女性がいた。
身体の線が細い。まっすぐな黒髪、切れ長の目――
よく似た誰かを知っているような気がするのに、意識はただ虚しく記憶の闇を掻くだけだった。
「ママー!」
彼はそう叫ぶと駆け出した。
父母と合流し、ふと思い出したようにこちらを振り返るや、
「ありがとー!バイバーイ」
小さな手を思い切り伸ばして振り回して、彼はまぶしいような笑顔と元気な声を残し、家族とともに楽しげに何ごとか言葉をかわしながら歩き去った。
紅子はなんとなくそのまましばし彼らの背中が見えなくなるまで見送ってから、ベンチのほうへ踵を返した。
ほんの一瞬の、他愛もない触れ合い。
だが、紅子はなぜか満たされた気持ちで、我知らず鼻歌まで歌っていた。
――誰もいないはずのベンチのそばに、人影を見るまでは。
長身で、どこか見覚えのあるシルエット。
まさか、と思いながらも、期待で心臓が跳ねるのを止められない。
日はそろそろ西に傾きつつあるとはいえ、水面の跳ね返す光はまだ眩しく、紅子は思わず目を細めて手庇ごしになんとか相手を確かめようとした。
眩しい視界の中、それでも彼のいつものいたずらっぽい笑みを視界に捉えた瞬間、紅子はほとんど衝動的にその名前を声に乗せていた。
「竜介!?」
すると、よく知っている声が答えた。
「久しぶり。びっくりした?」
紅子は驚きのあまり、文字通り心臓が口から飛び出さないように両手で口を押さえて呼吸を整え、それからようやく言った。
「びっ……くりした!」
電話やメールでずっと連絡を取り合っていたけれど、こうして実際に顔を見て話すのは本当に久しぶりすぎた。
耳元で心臓の鼓動が聞こえるのは、驚きのせいばかりではない。
「一瞬、向こうでなんかあったのかなって、縁起でもないこと考えちゃったよ」
照れを隠すように続けた言葉に、竜介は笑って、
「とりあえず、座って話そうか」
と、片手を差し出す。
「お手をどうぞ、お嬢さん。俺が幽霊かどうか、確かめてみたら?」
紅子は赤い顔で竜介の顔と手を交互に見てしばし逡巡してから、差し出された大きな手に自分の手を重ねた。
温かい。
竜介はにっこりして彼女の手を引き寄せると、滑らかな動作で彼女をベンチに座らせ、自分もその隣に腰を落ち着けた。
手は、重ねたままだ。
その温もりが、彼が本当にここにいるのだということを実感させてくれる。
――嬉しい。
が、同時に、どうしようもなく照れくさくて、つま先がむずむずする。
「いつ帰ってきたの?それに、なんであたしがここにいるって?」
黙っていると頭がオーバーヒートして妙なことを口走りそうなので、今一番の疑問を訊いてみる。
「今朝の便で」
と竜介。
「仕事が思ったより早く片付いた上に、一番早い飛行機に運良く空席があったんだ」
そして彼は帰国してからここに至るまでの紆余曲折を語った。
今日から日本は五月の連休だということは知っていたので、空港に到着後、都心に向かうリムジンバスの中で、竜介は紅子が家にいることを期待して一色家に電話をしたところ、紅子は出かけたという玄蔵の返事。
がっかりしたものの、もしかしたら出先で会えるかもしれないと思い直し、紅子の行き先を玄蔵から聞いておいて、とりあえずスーツケースなどを置きに、東京での定宿である虎光のマンションへ。
「ついでにシャワー浴びて着替えたかったし」
と彼が付け加えるのを聞いて、紅子は今日の彼の服装が長時間のフライト後にしてはこざっぱりしている理由を合点した。
ブルーのシルクシャツに濃紺のジャケット、灰褐色のコットンパンツに黒に近い濃褐色のレースアップシューズという出で立ちは、男物の服装に詳しくない紅子が見てもおしゃれだ。
「時差ボケは?」
「今回は仕事だったから平気」
竜介が酒好きが高じて海外の珍しい酒類を輸入する小さな会社を営んでいることは、付き合い始めてすぐに知った。
以前、彼の部屋で見かけた酒瓶の数々は、趣味と実益を兼ねたものだったのだ。
オフィスは彼の父方の祖父母が暮らすオーストラリアにあり、社員はいないいわゆる「一人社長」なので頻繁に日本と往復する必要があるけれど、時差はほとんどないから楽なのだと彼は言っていた。
紅子は言った。
「仕事だったんなら、別にわざわざ着替えなくてもよかったんじゃない」
「いやいや、飛行機に乗るときはよほど短時間じゃない限り、パジャマみたいな格好だから」
竜介は苦笑して頭を振る。
「それに、約束したからね。ちゃんとした格好で会うって」
部屋では虎光が連休を満喫していた。
出かける予定はないから車を使っていいとのことでお言葉に甘え、車でアウトレットモールに向かったが、着いてみると思った以上に広い上に混雑していて、もう直接携帯に連絡を入れようかと迷ったと彼は言った。
奇跡といってもいいようなことが起きたのは、そんなときだ。
『えっ?はい、いえ、別にそういうわけでは』
聞き慣れた声に振り返ると、家電量販店の店先にずらりと並んだ大小様々な液晶テレビすべてに、探していた人物が映っていた。
まるで、「彼女なら、ここにいるよ」と誰かが教えてくれているように。
彼はすぐさま傍らで呼び込みをしていた店員をつかまえて、画面に写っている場所への道順を聞き出し、人混みをかきわけて外に向かった。
そして今に至る。
不意打ちのような形で撮影された自分の姿が公共電波でさらされ、しかもそれを身近な人間が見たというのは、この上なく気恥ずかしく居心地の悪いものだ。
そのことについて紅子は不平を言ったが、竜介は、まあね、と一旦同意したものの、
「ま、俺はおかげでサプライズが成功したわけだけど」
と、いたずらっ子のように笑った。
「あれはほんと、びっくりしたな。奇跡的なタイミングだった」
「竜介が到着する前にあたしが移動して、入れ違いになってたら?」
「うーん、そのときはそのときで、電話すればいいかと思ってたんだけど」
竜介は少し口ごもってから、続けた。
「電話なんかしなくても、なんだか会える気がしたんだ」
紅子はまた自分の顔に血が上るのを感じた。
視界の端で隣にいる彼を盗み見ると、まっすぐ海を見ているその顔も赤らんでいる気がした。海からの照り返しのせいだろうか。
どう返事をしたらいいのかわからないまま、しばらく竜介の靴の隣に並んだ自分のスニーカーのつま先を見つめた。
もうちょっといい靴を履いてきたらよかった。
「……あとどれくらい日本にいられるの」
この質問を口に出すのは勇気が必要だった。
いつも帰国したと思ったらまたすぐに出国してしまって、学校がある紅子とはまったく時間が噛み合わなかった。
今回はたまたま会えたけれど、きっと今夜遅くか明日にはまたどこかへ旅立ってしまうんだろう。
そう思うと、別れまでの時間を自分から区切ってしまうような気がして怖かった。
でも、心の準備は必要だ――笑顔で彼を送り出すために。
声が震えないように、なるべく明るく尋ねた質問の答えは、しかし、いい意味で予想を裏切るものだった。
「しばらくいるよ」
と、竜介は答えた。
彼がここしばらく忙しくしていたのは、会社のオフィスを日本に遷すためだったらしい。
一緒にいられるのはとても嬉しい。
でも、なぜ今、日本に遷す気になったんだろう。
紅子がその疑問を口にすると、竜介はニヤリと笑うと、
「ま、年貢の納め時ってやつだよ」
それからふと真面目な口調になって、
「未来のことはわからないけど、自分の生活だけ考えて生きるのはもう潮時かなと思って」
どういう意味だろう、と紅子が考える暇もなく、彼は
「親父のこともね」
と続ける。
「君の親父さんから言われたよ。俺がいつまでも苦しむことを、死んだ母さんが望んでいると思うのかって」
短い沈黙が降りた。
いつの間にか海の向こうは夕焼けの色が濃くなり、周囲の喧騒も遠のいたようで、波の響きだけがやけに大きい。
それを破ったのは、紅子だった。
「あたし、黄根のおじいさんから遺品をもらったの。古い写真なんだけどね」
玄蔵が母親の墓参をしたあの日、禁術が使われることで起きる変化――御珠の消失、時系列の変化など――についても事前に説明しておくことで混乱を最小限にとどめようとしたのだろう、黄根老人は泰蔵のもとを訪れた。
そのとき同時に、彼は自分が死ぬことも予言し、
「すべてが終わって落ち着いたら、紅子に渡してほしい」
と泰蔵に託したのが、その写真だった。
東京に戻る前に泰蔵から手渡されて以来、紅子はそれをなんとなくお守りのようにパスケースに入れてずっと持ち歩いていた。
今、彼女はそれを取り出し、改めて目を落としていた。
そこに写っているのは、赤ん坊を抱いた若い夫婦だ。
色は褪せ、何度も折り畳んだり開いたりされたらしく、折り目の部分が白くなってはいるが、画面の中の笑顔の女性が若い頃の祖母であることはすぐにわかった。
そして、写真の裏には、「日奈の宮参り」と書いてあった。
「黄根のおじいさんは、きっとわかってもらいたかったんだと思う。母さんやあたしのことをどれくらい大切に思っていたか」
「そうか……」
竜介はため息とともにそう言って、頭を掻いた。
「俺、あの人に悪いことしたな。娘の幸せなんかどうでもよかった、なんて決めつけて」
夕日は彼らの背後に遠のき、辺りは急に暗くなり始めていた。
竜介は紅子が持っている写真をよく見ようと少し身を乗り出す。
と、そのとき――
いきなり風が強くなり、一陣の突風が砂埃を巻き上げた。
紅子は小さく悲鳴を上げ、思わず強く目を閉じる。
その瞬間、手にしっかり持っていたはずの写真が、風にさらわれて舞い上がった。
「写真が!!」
紅子は慌てて手を伸ばし、空中をひらひらと滑っていく写真を追いかけたが、もう遅い。
それは風に流されるまま柵を乗り越え、夕暮れの暗い波間に消えた。
紅子がなすすべもなく柵にもたれて、写真が消えていった海を呆然と見つめていると、隣に竜介がやってきて言った。
「黄根さん、よほど俺に見られるのがいやだったのかな」
冗談なのか本気なのかわからないとぼけた口調に、紅子は思わず吹き出した。
「照れくさかったんだよ、きっと」
それに、と続ける。
「わかってもらえたからもういい、と思ったんじゃない?」
「だといいんだけど」
会話が途切れたが、そのまま二人は並んで暮れていく海を見ていた。
静かだった。
コンクリートに打ち付ける規則的な波の音のほかは、モールのほうから聞こえるかすかなざわめきばかり。
帰りたくない。
そんな言葉が口をついて出そうになる。
が、それはさすがに彼を困らせるだけだろうと、紅子は代わりの言葉を探した。
「ずっとこんな日が続くといいのにね」
すると竜介はふと微笑んで、
「続くさ」
と、答えた。
それから改まった様子で
「紅子」
と彼女を名前で呼ぶと、少しためらいがちに言った。
「……キスしていい?」
「え、ここで?」
紅子は真っ赤に上気した顔をごまかすように、慌てて周囲を見回す。が、
「誰もいないよ」
と竜介が言う通り、いつの間にか辺りは人の気配が絶えてひっそりしていた。
自分の心臓の音が、彼にまで聞こえるのではと心配になるくらい。
「ど、どうぞ……?」
紅子が思い切って答えると、肩に温かな手が置かれて、竜介の顔が間近に降りてきた。
その端正な顔が、困ったような笑みを浮かべている。
前にも、こんなことが――
そう思っていると、
「前にも言ったと思うけど、」
と彼が言った。
「やりにくいから、目を閉じてくれるかな」
驚きのあまり、言われたこととは真逆に、紅子は反射的に目を見開いた。
「前にも、って……!?」
でも、あれは夢だったはずでは?
「その話は、またあとで」
竜介はいたずらっぽく笑うと、自分の唇の前に人差し指を立てた。
「今は……目を閉じて」
そうだ。これから、時間ならあるんだった。
そう思いながら、紅子はゆっくり目を閉じる。
話したいことはたくさんあった。
もしかしたら、一生かかっても尽きないほどに。
夕焼けの残照を背景に、二つのシルエットが重なった。
海を渡る初夏の風が、暖かく二人を包んでいた。
季節はまだ始まったばかりだ、と言うように。
<完>
※挿絵はAIに寄るものです。





.jpg)

















.jpg)
.jpg)
.jpg)
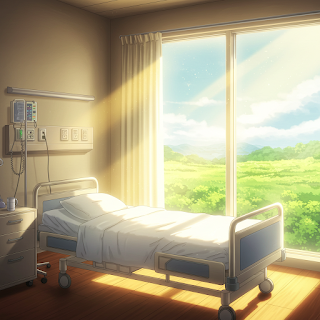
.jpg)




.jpg)