まる四日眠っていた、と医者から告げられたときは自分の耳を疑った。
診察の結果、医者は紅子をまったくの健康体だと請け合って、彼女の身体に取り付けられていた管やセンサーを外してくれたあと、
「今夜一晩様子を見て問題なければ、明日の午後退院しましょう」
と言って、看護師を連れて病室を出て行った。
入れ替わりに父と祖父、それに虎光が入ってきたので、紅子は竜介と鷹彦、白鷺家の二人、それに黄根老人の安否を尋ねた。
三人が一瞬、微妙な表情になったので不安になったものの、なぜかなんとなく彼らの返答を予測できた。
そして彼らは、紅子が直感した通りのことを言った。
五人のうち四人は無事で、元気にしている。
ただ、黄根老人だけが亡くなった、と。
紅子は、なぜ、とも、いつ亡くなったのか、とも尋ねなかった。
それより、父親以外で母や祖母のことを知っている親族がいなくなってしまったことが、ただ残念で悲しかった。
「そう……」
と言ったきり、悄然と黙り込む彼女の目の前に、虎光が気まずい空気を変えようとして差し出したのが、例のギフトバッグだった。
「兄貴から、紅子ちゃんに渡してくれって預かったんだ。直接渡せてよかったよ」
虎光はそう言って、開けてみるように促した。
父親と祖父もいる前で、どう見ても特別感あふれるギフトバッグを開けるのは照れくさかったが、自分も中を見てみたい気持ちが勝って、紅子はベッドの上に起き上がると、紙袋の口の部分を閉じている小さなテープを剥がした。
これまでの自分の人生で、開封の瞬間にこれほどドキドキしたプレゼントがあっただろうか、と思うくらい、それは胸の高鳴る一瞬だった。
袋の中身は、電話会社のブランドロゴが印字された化粧箱。
それと、水色の封筒に入った手紙が一通添えられている。
箱を開けると、中にはパールが入った臙脂に金属部分がゴールドというおしゃれなフリップ式携帯電話が収まっていた。
電話をかけろってこと?
周りの視線を忘れて、紅子は急いで封筒を開けた。
封筒と揃いの水色の便箋が四つ折りになって入っていたが、それを開くのももどかしい。 紺色のインクを目で追いながら、そういえば竜介の肉筆を見るのはこれが初めてだと思う。
男性らしいカチッとした文字で、そこにはこう綴られていた。
一色紅子様
今、君は目を覚ましてこれを読んでくれていることと思います。
本当はこの手で渡したかったけれど、用事で日本を離れることになり、虎光に託しました。
俺は君のそばにいられないのがとても残念ですが、君はどうかな?
もし少しでも残念だ、寂しいと思ってくれるなら、この手紙に同封した携帯電話で連絡をください。
あの夜の月を、また一緒に見られることを願って。
愛しています。
紺野竜介
文字通り、本当に顔から火が出るかと思った。
最後の一文に目を通すや否や、紅子は電光石火の早業で便箋をベッドの上に裏返しに伏せた。
顔を上げると、祖父も虎光も、わざとらしく明後日のほうを向く。
父だけがなんとも複雑な顔で自分を見て、何か言おうとしたのか口を開きかけたが、
「えーと、そういえばそろそろ、面会時間も終わりだな。玄蔵、虎光くん、帰ろうか」
という、なんだか妙に上ずった泰蔵の言葉で遮られてしまった。
虎光も調子を合わせて、
「あ、ですね。じゃあ俺、車だから送っていきますよ」
だが、
「えっと、待って待って」
紅子は慌てて呼び止めると、まだ電源が入っていない携帯電話のフリップを開いて見せて言った。
「虎光さん、すみませんが使い方を教えてもらえますか?」
携帯が入っていた箱には使い方を書いた小さくて分厚い冊子も同梱されていたが、そんなものを読み込む時間が惜しかった。
電話でもメールでもいいから、今すぐ使いたい。
虎光は快く、さしあたって必要と思われる機能を手短に教えてくれた。
その間、玄蔵が直ぐ側で
「携帯電話なんてまだ早い」
だの、
「退院してからでもいいだろう」
だのぶつくさ言っていたが、聞こえないふりをした。
電源を入れてみると、メールの着信が一件あった。
中身は、竜介の名前と携帯電話の番号だけ。
「兄貴はまだ国内にいるから、電話したら喜ぶと思うよ」
虎光に言われるまま、紅子は恐る恐る、画面の番号に電話をかけた。
電話を耳に当て、緊張した面持ちで呼び出し音を聞いている紅子を残して、泰蔵と虎光は狼狽する玄蔵をなだめつつ、その背中を押すようにして廊下に出た。
電話はまもなく繋がったようだ。
紅子が小さな声で、電話の相手に何事か話しかけるのが聞こえた。
その後、嬉しそうに何度も頷き、目尻に浮かんだ涙を指で拭う様子を肩越しに確かめると、虎光は病室の引き戸を後ろ手にそっと閉めたのだった。
* * *
それから約二ヶ月以上経って、紅子はようやく東京に戻った。
三月も半ばになろうかという頃である。
なぜそんなに時間がかかったかといえば、端的にいうと、家が住める状態ではなくなってしまっていたからだ。
黒珠が引き起こした未曾有の大寒波は、大量の積雪と寒さによって、送電や上下水道などのライフラインを傷つけたほか交通網を寸断し、古い家屋などを破壊した。
のみならず、気温が年明けとともに平年並みに戻ったあともなお、大量の融雪水による浸水が起き、人々の生活に甚大な被害をもたらした。
そしてその被害は、一色家にも及んでいた。
政府が発した緊急避難指示は、二月には全面解除となったので、東京の本社まで様子を見に行くという虎光に頼んで、玄蔵と紅子も彼の車で同行させてもらったことがあった。
一色家は倒壊こそしていないものの、もともと古かった建物は、屋根が雪の重みで素人目にもわかるほどたわんでいたし、家の中も、雪によるものか浸水のせいかは定かではないが、一階部分はとても人が住める状態ではなくなってしまっていたのである。
そして、例の土蔵に至っては、ただの瓦礫の山と化していた。
幸い、玄蔵が「一色流練気柔術」の道場として借りている建物は無事で、中にはシャワールームもあり、手狭だが当面の生活ができる程度の設備はあるので、自宅の改築が完了するまではそこに住むことで一応の解決を見た。
それでも不便な生活はできるだけ短期間であるに越したことはない。
道場の再開をしなければならない玄蔵は二月半ばには東京に戻っていたが、紅子は学校が始まるギリギリまで泰蔵のところにとどまっていたのだった。
とはいえ、一色の家を建て直すかどうかについては、玄蔵はかなり悩んだようだ。
深夜、泰蔵と相談しているのを、紅子は何度か見かけた。
泰蔵の家から通える高校への編入手続きを促す書類が役所から届いているのを見かけると同時に、東京の高校からも、四月に授業再開の見通しが立ったという連絡が来ていたが、どちらがいいかと訊かれれば、紅子にとっては後者がいいに決まっている。
玄蔵にとっても、新しい場所で一から道場の経営を始めるよりは、すでに弟子たちがいる東京に戻って、完全に元通りとまでは行かずとも、道場を再開するほうがずっと楽なはずだ。
残る問題は先立つものだったが、玄蔵が自分の生家の名前を出すと、驚くほどすんなり銀行の融資が通ったそうで、それが最後の決め手となったのだった。
泰蔵だけは、息子や孫といっしょに暮らせる当てが外れて、少し落胆したらしいけれど。
東京に戻った紅子は、改築が始まる前の更地になった自宅跡地を見に行ってみた。
築地塀はなくなり、代わりに周りを囲っているのは仮説された蛇腹式の横引きシャッターで、その向こうに広がる空き地は驚くほど広かった。
植栽もほぼ取り除かれ、隅の方に真新しい建材がいくつか置かれているほかは本当になにもない。
土蔵があった辺りの地面も、それらしい穴の跡はない。
「何もないぞ」
出かける前、家の跡を見に行ってくる、と言う紅子に、玄蔵は言った。
それに先んじて、彼は他にも、「去年の冬至と新月は重なっていない」ことを新聞などの月齢カレンダーで調べて教えてくれていた。
そう、世界は変わったのだ――御珠の存在しない世界に。
※挿絵はAI画像です。
.jpg)
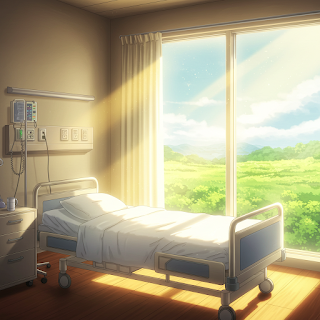



.jpg)